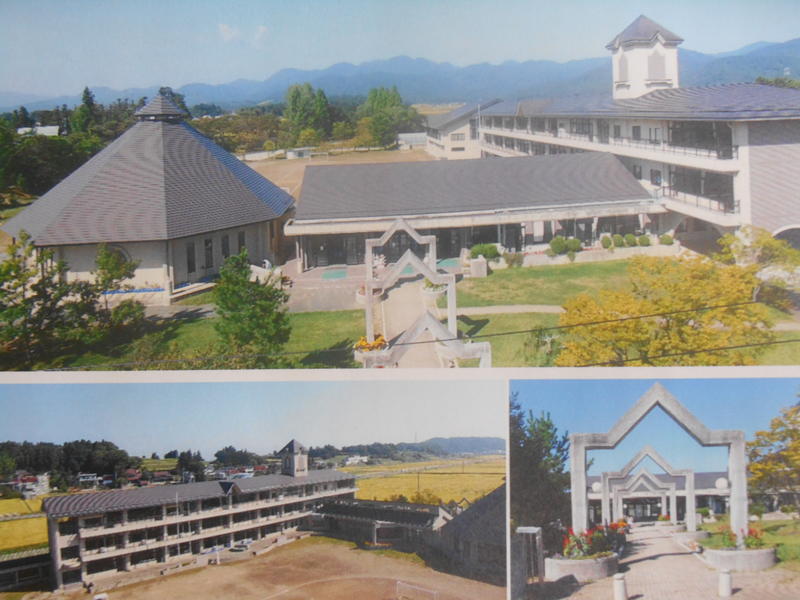本校では、「食育」や「よい歯の指導」、地域の方々との交流を通してのコミュニケーション力の向上等、さまざまなねらいのもと、80歳で自分の歯を20本以上持っている地元のお年寄りを招いて、「8020ふれあい給食」を行っています。
今日は、岩瀬歯科の太田久美子先生や地元の「8020講師」5名の方、須賀川市教育委員会の森尾さんがおいでになりました。4年生と6年生の教室に分かれて、子どもたちと給食を召し上がっていただきました。子どもたちからは、「日頃、歯の健康のために気をつけていることは何ですか?」とか「昔は、どんなおやつを食べていましたか?」などの質問が出され、ていねいにお答えいただきました。
また、今週は「白方小希望献立ウィーク」で、今日の献立(麦ごはん・牛乳・いわしのごまみそ煮・はくさいとニラのおひたし・けんちん汁)は、6年生のグループが考えたものでした。
合わせて、「いただきます。ふくしまさん」という県の事業ともタイアップしました。この事業は、食育の推進や東京電力福島第一原子力発電所事故の影響による学校給食への不安を軽減することを目的としたもので、本校の今日の給食の食材も、例えば、米・白菜・ニラ・大根・ごぼう・ねぎ・こんにゃく・とうふは須賀川産、にんじんは鏡石産、豚肉は県内産、というように、県産・地場産のものをできるだけ使いました。
なお、他学年は岩瀬給食センターの上遠野栄養士による食育の指導が行われました。